|
同じ穴のムジナ 人々の往来が盛んなる駅構内にて、若い女が一人、不安げに待ち合わせ用のオブジェを見上げていた。彼女はくりっとした瞳が印象的な丸顔で、薄手のシャツにぴったりとしたジーンズを合わせており、たすき掛けに下げた鞄の紐が本来は控えめな胸元をいくらか強調している。見た目の程は、二十代の半ばといったところだろうか。 「『銀の鈴』って、多分これやんな? うん、どう見たってこれ、銀の鈴やんな?」 大阪から来た丸顔は誰に言うでもなく漏らし、自分の集合時間場所が間違いないことを己に言い聞かせて安心を得ようとしていた。 『@foxy_voice 到着したで〜ヽ( ̄▽ ̄)ノ』 そしてもぞもぞ携帯をいじり、今日会うべき人に向けて呟いた。するとすぐさま、次の通りに返ってくる。 『@ponpoko_kinu ひょっとして、パンダみたいな服着てる女の子?』 そう言われて丸顔の彼女は、自分の服装を省みた。シャツは胴が白くて、半袖だけ黒い。パンダみたいと指摘されればその通りかもしれないと思う。なんだか少しバカにされているような気持ちにモヤッとなりつつも、そうだと呟くと、間もなく近場のベンチから女が立ち上がってきた。 「あなたが絹子(きぬこ)さん? 初めまして。私は音々(ねね)です」 声かけられた丸顔・絹子は振り向くと、まず息を呑んだ。一目みて、えらい美人だと思ったからだ。手足はすらりとしたモデル体型で、切れ味のある顔に施された適度な化粧。さらには膝丈までの色合い華やかなワンピースと黒いベルトの合わせ――絹子の持つ素朴さとは正反対の女性的な魅力を、音々は明らかにして隠さない。見た目の程は、絹子よりもややお姉さん的と言えようか。 音々はそんな色香を振り撒きつつも決して鼻にはかけず、柔和な微笑みを浮かべたままあいさつをした。 「東京はどう? 迷わなかった? ……って、あれ?」 ところが不意に、ちょっとだけ鼻をひくつかせた後で、眉をひそめるのだった。 「……あなたもしかして、タヌキ?」 頬も触れんばかりに顔を寄せると、音々はそう囁いた。ちなみに“タヌキ”の“タ”にアクセントを置いた喋り方である。 対して絹子は問い詰められたタイミングに驚き、またその内容の正しさに怯えすらした。 「ちょ、なんでうちがタヌキって分かっ――」 小声で返そうとした絹子だが、その言葉は最後まで続かない。途中で彼女の鼻も、香水に混じってひっそり漂う匂いを特徴的に捉えたからだ。ちなみにこちらは“タヌキ”の“ヌ”にアクセントを置いた喋り方である。 「あんたひょっとして……キツネ?」 絹子が問うと、音々は無言で肯定した。 それぞれが指摘し納得した通り、彼女らは人間ではない。絹子は化けダヌキである。妖術によって己の身を変じ、古より山野に現れて人間を惑わすとされてきた。その伝説通説は人知れぬ事実であって、今なお継がれる妖術の強さは衰えない。しかし昔に比べて山暮らしが難しくなっているのも事実であり、若者の中にはこうして人間に交じっての街暮らしを選ぶ者も少なくないのである。片や音々は化けギツネである。妖術によって己の――中略――である。 「な、なんでキツネがこんなとこおんねん!!」 「それはこっちの台詞よ。まさかタヌキが来るなんて聞いてないわ」 まず絹子が退いて吠え、音々もまた毛を逆立てて応じる。タヌキとキツネといえば、人間を化かすモノノケとして有名も有名な双璧である。それ故に当然意識もするし、長らくライバルとして競い合ってもいたものだ。 そうしてしばしの間、両者はにらみ合ったが、その緊張を解いたのも絹子が先だった。 「……なあ、そろそろ止めへん? こういう、ここで会ったが百年目〜みたいなノリ」 「そうね。正直に言うと、私も別に個人的にタヌキに恨みがあるわけじゃないし。わざわざ喧嘩をしに来たわけじゃないんだから、お爺さんお婆さんの代のいざこざは脇に置いときましょうか」 なにせ先祖伝来の確執よりも目先の好楽を重んじる妖怪ゆとり世代。化け比べで山の覇権を争っていた時代のことになど、良くも悪くも頓着しないのであった。 さてそもそも、どうして素性を知らぬ者同士がこうして落ち合うことになったのかといえば、これまた別段にモノノケの誇りや伝統とは全く関係の無いことであった。大人気アイドルグループのコンサートチケットを運良く手に入れた絹子が、せっかく上京してまでの一大イベントなのに一人で観るのはつまらないと思い、電子掲示板にて同行者を募った結果がこれである。 「あ〜やっぱ格好良かったわ〜。多野くんめっちゃ可愛かったわ〜。なぁ見てた? タキシードのボタン一個かけ違えとったやんな?」 「見えてた見えてた。一度袖に引っ込んでからまた出てきたときには、ちゃんと直ってたわよね」 「多分めっちゃ急いで直してんで」 あれが良かった。ここが好きだった。あそこは面白かった。あっちはむしろああしたほうが良かったんじゃないか――絹子はケラケラと、音々はクスクスと、笑いつつそんなこんな感想を語り合い、祭りの後の余韻を楽しむ。 「そういえば絹子は今夜どうすんの? これから大阪まで日帰りってのは厳しいよね?」 気がつけば、もう空はとっくに暗い。 「うん。せやから、ちゃんと休みは取ってあるで。今日は適当なホテルに泊まって、明日はお土産買うて帰るねん」 「そう。私は明日も仕事だからあんまり長居は出来ないけど、夕飯くらいは一緒に食べられるわよ」 音々から食事を誘われてようやく、絹子は己の空腹を自覚した。 「東京で何かオススメのんある?」 「蕎麦はどうかしら。この辺りで、いいお店を知ってるのよ」 「蕎麦か……うん、たまには蕎麦もええね」 そして口元に指を添え、やや思いを巡らせて、絹子は快諾した。 二人で藍色の暖簾を潜り、からからと戸を開けた。 音々が案内した蕎麦処は、日が沈んでもなお活気に満ちていた。調理場からの湯気が香るカウンター席にはサラリーマンが並び、奥まった座敷からは家族連れの談笑が漏れて聞こえる。大通りを一つ外れて目立たぬ場所に立ちながらも、これだけの人気があるのは味にも期待が出来るということだ。 「ここええやん。食べよ、食べよ」 空きっ腹に店の空気を吸い込んだ絹子は、辛抱たまらずと言わんばかりにレジ横の席を陣取った。音々は小さく息を吐きつつ、その隣に腰を下ろす。 そして絹子は品書きを開き、さらっと目を通して特に深く考えずに注文した。 「ほな、せっかくやから、うち『たぬき』」 「じゃあ、私は『きつね』にするわね」 合わせて音々も好きなものを適当に頼んだ。 さて問題は、それぞれの前に『たぬき』と『きつね』が運ばれてからの話であった。 「ここの『きつね』はね、蕎麦と汁(つゆ)と油揚げ、三拍子がハイレベルで揃った逸品なのよ。派手さは無くてもファンが多いの。私もその一人よ」 音々はそう誇らしげに言うのだが、その脇で絹子は固まっていた。辛うじて口角だけが引きつっているようだ。「これ、何なん?」 絹子がこれ呼ばわりしているのは、もちろん彼女の卓に置かれた『たぬき』である。 「『たぬき』でしょ?」 「ほんで、そっちのは?」 「私のは『きつね』」 絹子はぎりぎりとゼンマイ仕掛けのように首を回し、何度も卓上の『たぬき』と『きつね』を見比べた。どちらも暖かくて潤沢な濃口の汁に、香りの高さを窺える蕎麦が入っている。違いはといえば、『たぬき』には天かすがたっぷり盛られていて、『きつね』には油揚げが乗せられているところ。 「なんでやねん!!」 しかして絹子にとっては、それこそ納得いかない点であり、また期待を大きく裏切られた結果なのだ。 「あ、ありえへん……うち、『たぬき』頼んだはずやのに……」 「だから『たぬき』でしょって」 「これが? ちゃうやろ。それになんで音々の『きつね』やのに、蕎麦なん?」 「は?」 「『きつね』言うたら、うどんやん」 「そんなの決めつけないでよ。だいたい、この店はうどん出してないわよ。蕎麦の専門」 「え、ほな、なんで『きつね』なん?」 「ん?」 「え?」 互いの聴き方が全く噛み合わなかった。 「『きつね』言うたら、うどんのことやんか」 「また同じこと言って、」 「いや、ちゃうねん。ちゃうねん。音々のは『きつね』やなくて『たぬき』やねんて」 「どう見たって『きつね蕎麦』でしょうよ」 「『きつね蕎麦』なんてもんは存在せえへん!!」 「はぁ?」 眉をひそめた音々の声には、一層の怪訝さがあった。 「油揚げの乗った蕎麦――これが『たぬき』だとしたら、絹子のは何だってのよ」 だが絹子もここでは退かない。 「うちのはただの、天かす入りの『かけ』やん。『天かす蕎麦』言う人もおるけど」 「だからそれを『たぬき』って言うんでしょ」 「ちゃうねんて」 「……私のが『たぬき』で、あなたのが『かけ』だとして、じゃあ『きつね』は?」 「うどん」 さも当然とばかりに言い放つ絹子に、頭を抱える音々。 「待って、待って。一回落ち着いて、行きつけの病院の番号は言える?」 「うちはまともやっちゅうねん」 「はいはい。それで、なに? え、『きつね』が『たぬき』で『たぬき』が『かけ』? うん、意味が分からないわ」 「せやから、おかしいねんて」 「おかしいのは絹子よ。何なの?」 「何なのって、何やの?」 絹子の眉間にしわが寄る。銀の鈴の前で正体を知り合ったとき以上の緊迫感が張り詰めた。せっかくの楽しいコンサートの帰りに険悪な雰囲気になることは避けたいので、今回は、おそらく年上であろう音々が建設的に話を進めようとする。 「ちょっと整理しましょうか。油揚げが乗ってるのは『きつね』でしょ。それはOK?」 「オッケー」 「そこの認識は合ってるのよね」 じゃあこれは、と音々は自分の前にあるもの――油揚げの乗った蕎麦を指す。 「それは『たぬき』や」 「なんでよ!!」 「蕎麦やもん!!」 「意味が分からない。油揚げは『きつね』だって、さっき確認したじゃないの。あなたもそれでOKしたじゃないのよ」 「せやから、お揚げさんの乗ったうどんが『きつね』で、蕎麦が『たぬき』やんか」 「そんな区別は普通しないわよ」 「ほな東京がおかしいねん」 「大阪が変なんでしょ?」 「変ちゃうわ。お釈迦さまに訊いたかてそう言うっちゅうねん。あーうちは騙されへん。騙されへんでー」 言いながら絹子は自分の指に唾をつけて眉に塗っている。 「あなた、わざわざ喧嘩を売りに来たの?」 「それとこれとは話が別やで。うちの地元じゃみんな『たぬき』『きつね』って、そう呼んどったんやから」 「じゃあ『たぬきうどん』のことはどう言うの?」 「『たぬきうどん』なんてのも存在せえへんよ」 絹子の堂々とした言い方に、音々はちょっとしためまいを覚えつつも努めて冷静であろうとした。 「訊き方を変えるわね。大阪で天かすの乗ったうどんや蕎麦を注文するときは、どう言えばいいの? 『かけうどん』とか『かけ蕎麦』と言えばそれが出てくるの?」 「天かす入りのなんていちいち注文せんよ?」 「ますますもって謎だわね。その天かすはどこから湧いて出るのよ」 「そんなもん、セルフで自由に入れればええやんか」 「え、もしかして天かすが無料なの!?」 「当たり前やんか。牛丼屋さんで紅しょうが追加で頼んだり、カレー屋さんで福神漬けに金払ったりせんやろ? それと同じやで」 絹子の主張によれば、地元では天かす入れ放題の店が普通だとのこと。であるからして彼女にしてみれば、何の前説明も無くワンランク下の価値のものをででどんっと出されたということであり、馬鹿にされたような心地であった。それはもうムカッ腹は立つし、思わず「なんでやねん」が口を突いて出るのも道理であろう。 「ってことは、何? 東京じゃ天かす、タダちゃうん!?」 「そうよ」 「うわ、ケチくさっ!!」 「別に、普通でしょ」 「あかんわー。天かすで金取るなんて、お釈迦さまが聞いたら怒るわー。これやから東京もんはなー」 「あなたのところのお釈迦様は、どれだけ食い意地が張ってるのよ」 何故か優越感を抱いている絹子のしたり顔に、音々は得も言われぬ苛立たしさを感じた。 「とりあえず、なんとなく分かってはきたわ。つまりこういうことでしょ?」 だがそれはそれとして、音々は紙ナプキンを取り、その上にペンを走らせた。 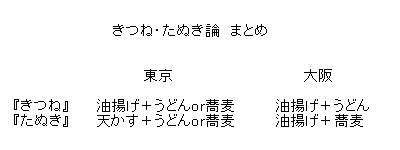
書かれた表を覗いて、絹子も頷く。 「せや、せや。こういうことやねんな」 「でも、なんだかね。やっぱり違和感があるわよね。『きつね』と『たぬき』の違いがうどんか蕎麦か、なんてさ……だって、意味が分からないもの」 「なんやの、意味分からんって」 「由来の話よ。キツネと言ったら油揚げ。だから『きつね』は油揚げがあれば、うどんも蕎麦も問わない。そして『たぬき』は『タネ抜き』の略なんですってよ。中身の入っていない天かすを入れたものだから『たぬき』。どちらも具材と名前にしっかりと意味があるわ」 得意げに語る音々だが、しかし、あくまで彼女の話も諸説の一つに過ぎないことは留意すべきであろう。 「それに引きかえ、『きつね』がうどんって何よ。『たぬき』が蕎麦って、何の謂れがあるわけ?」 「そ、そんなん知らんくたって、関係ないやんか」 「答えられないでしょ? ほら見なさい。私の勝ち」 「いつから勝負になってん!?」 このままでは一方的に貶められるような気がして、何か反撃の論拠は無いかと、絹子は頭を回した。 「せや、うちは知らんくても、世間ではちゃんと言うてるで。ほら、よう考えてみ。マルちゃんの『赤いきつね』はうどんで、『緑のたぬき』は蕎麦やんか。な?」 これでどうだと言わんばかりに、絹子はカウンター卓に肘をついて、身を乗り出して食いつくように音々に寄った。 「あ、確かにそうね」 「せやろ? せやろ?」 「でも『赤いきつね』は油揚げで、『緑のたぬき』は天ぷら、かき揚げよ」 「……せやねん」 そして今度は、奥歯を噛んで心底悔しそうにうな垂れた。 「そもそもね、タヌキのくせに油揚げってのが変なのよ」 それを音々は、ふふんと鼻で笑った。明らかに見下した様子である。 「タヌキのくせに……って、言うてええことと悪いことがあるやんか」 うまいことが言えない歯がゆさと不甲斐なさとで進退極まっているところで、音々からのダメ押しを食らう。 「もう我慢の限界や。堪忍袋の緒ぉ切れた」 これまでは『たぬき』対『きつね』、あるいは東京対大阪という地域文化での摩擦だったが、この期に及んで種としてのタヌキに言及されれば、抑えていた感情が沸き立つのを止められない。 「今日こそは、今日こそはタヌキ四千年の歴史を代表して言わしてもらうで」 「な、なによ」 瞳に宿るめらめらとした闘志は絹子の本気を窺わせ、さすがの音々も僅かにたじろいだ。 絹子の拳がぎゅっと固まる。 「タヌキかて、タヌキかてなぁ……お揚げさん大好っきゃねんで!! お揚げさんは、キツネだけのもんとちゃうねんで!!」 「四千年の歴史を背負って言うことがそれ!?」 「大事なことやんか。大事なことやんか!!」 大事なことである。 「キツネはいっつもそうや。好物かなんか知らんけど、いっつもキツネとお揚げさんがセットみたいになっとる。独り占めはズルいんとちゃうか? 言うたらうちらの好物もお揚げさんやねんで? せやのに、お揚げさんの乗ったうどん頼もう思たら、そのたびに『きつね』言わなあかんタヌキの気持ち考えたことあるん? 戦う前から負けたみたいな感じなるねんで。そんな屈辱をずっと強いられてきてんねんで?」 「そんなの知らないわよ。っていうか、だったら地元に帰って『たぬき』を注文すればいいじゃないのよ。油揚げの乗った蕎麦が出てくるんでしょ? それでいいじゃない」 「……うどんも好っきゃねん」 「面倒くさいわね!!」 怒りや敵対を通り越して、今や音々の気持ちは呆れ一杯であった。これ以上はまともに相手をしたくないのに、向こうからはぎゃんぎゃんと噛み付いてくるものだから、どうしてくれようかとも思った。 「というか、絹子。いつまでも喋ってないで食べましょうよ」 いっそ注意を逸らしてしまおうとの結論に至る。 「なんや、音々。まだ話は終わってへんで。うちは腹わた煮えくり返っとんねん」 「いいから、のびちゃうわよ」 ちょっと強引にでも、音々は勧めた。 「あんなぁ、うちが食べたかったのは『たぬき』。お揚げさんの乗った蕎麦やねん。あの、噛むごとにジュワァ〜広がる大豆の旨みと油の香り――それを受け入れる口になってもうとるのに、何が悲しうて天かすなんか食べなあかんのん? おかしい。世の中おかしいで、これ。だいたいなんや、この真っ黒い汁は? もっと、こう、お出汁を利かせた繊細さってもんがあるべきやんか。それをこんな醤油に頼った味付けなんかして……」 ぶつくさと不満を漏らしつつも、渋々、絹子は蕎麦をたぐる。 「…………旨いやん」 「でしょ?」 そして憑き物が落ちたように穏やかさを取り戻した絹子は、それ以上に文句を言うことなく食べ進め、しまいには汁の一滴まで残さず平らげた。 * さてここに、以上の会話劇を横で聞き耳立てていた男がいる。彼は小太りのスーツ姿で、目の下に大きな隈がある。絹子と音々が上機嫌で店を去ってから間もなく、男の卓に注文の品が運ばれてきた。 「へい。『むじな』お待ち!!」 威勢良く置かれた丼ぶりの中身は、かけ蕎麦の上に油揚げと天かすの両方が乗せられているものだ。『たぬき』と『きつね』の具材をどちらも堪能できる『むじな』は、東京でもマイナー寄りの、知る人ぞ知る品目である。 それを一口食べてから男は、二人がいなくなった後の空席に目を移し、誰に言うでもなく独り呟いたのであった 「同じ穴のムジナ」と。 「同じ穴のムジナ」 橘圭郎・作 妖怪【タヌキ】【キツネ】 戻る |